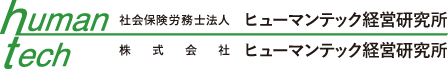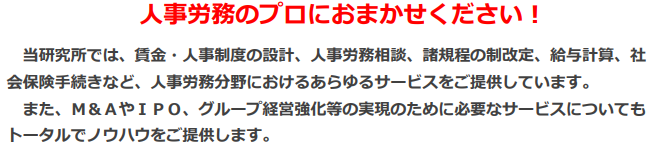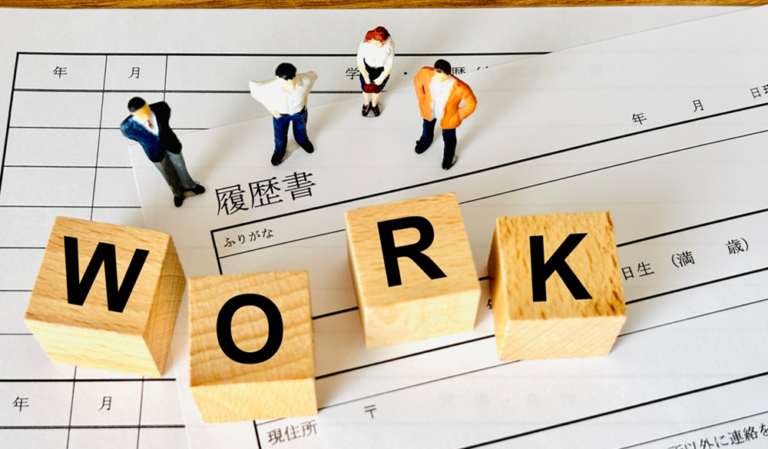2025.07.01
法改正情報
【2025年6月成立】女性管理職比率などの情報公表が義務化されます ~改正女性活躍推進法の概要~
本年の国会で成立し、6月11日に公布された「労働施策総合推進法等を改正する法律」※1により女性活躍推進法が改正され、2026年4月1日以降順次施行されます(一部は公布日に施行済み)。本改正は、女性管理職比率の公表が事業主に義務づけられるなど、実務に大きな影響があります。
そこで今回は、改正女性活躍推進法の概要と女性活躍推進法に基づく認証制度の概要(えるぼし認定)について解説します。
▽次回コラムをチェックする▽
【2025年6月成立】「えるぼし」認定基準が改正されます ~改正女性活躍推進法の概要~
1.女性活躍推進法の概要
女性活躍推進法※2とは、女性の活躍の推進についてその基本原則を定めるとともに、国、地方公共団体、企業に対して女性が活躍するために実施すべき事項を定めた法律であり、2016(平成28)年4月1日から2026(令和8)年3月31日までの10年間の時限立法です。
女性活躍推進法では、常時使用する労働者が101人以上の企業に対して、以下の2点を義務づけています。
| (1)女性の活躍を推進するための一般事業主行動計画の策定・届出 |
| (2)自社の女性の活躍状況に関する情報公表 |
なお、100人以下の企業については、いずれも「努力義務」とされています。
2.改正法の概要
それでは、改正女性活躍推進法のうち、とくに実務への影響が大きい情報公表項目の拡大等について見ていきましょう。
(1)有効期限の延長
女性活躍推進法の期限が10年間延長され、2036年3月31日までとされました。
(2)情報公表項目の拡大等
情報公表とは、1.で見たように女性活躍推進法で義務づけられている事項の一つで、自社の女性の活躍に関するデータを社外に向けて公表することです。情報公表する項目は全部で16項目あり、以下の2つの区分に分類されています。
| ① 女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供(9項目) |
| ② 職業生活と家庭生活の両立(7項目) |
現行法では、常時雇用される労働者が301人以上の企業の場合、①の区分の項目である「男女の賃金の差異」を必ず公表する必要があり、さらに上記①と②の区分ごとに任意の項目を1つずつ、合計3項目以上の情報を公表する必要があります。一方、101人以上300人以下の企業および情報公表が努力義務とされている100人以下の企業は、すべての項目から任意の1項目以上の公表でよいこととされています。
この情報公表について、改正後は、101人以上の企業に対して新たに以下の2点の情報を公表することが義務づけられます。
| ・男女間の賃金差異 |
| ・女性管理職比率 |
改正前後の情報公表項目を企業規模別に見ると、次のとおりです。
【図表1】改正前後の情報公表項目(下線は変更箇所)
| 企業規模(公表義務の有無) | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
|
300人超(義務)
|
・男女間の賃金差異(必須)
・①、②のそれぞれの区分から任意の項目を1項目以上(合計3項目以上)
|
・男女間の賃金差異(必須)
・女性管理職比率(必須)
・①、②のそれぞれの区分から任意の項目を1項目以上(合計4項目以上)
|
|
101人以上300人以下(義務)
|
・①、②のすべての項目から任意の項目を1項目以上
|
・男女間の賃金差異(必須)
・女性管理職比率(必須)
・①、②のそれぞれの区分から任意の項目を1項目以上(合計3項目以上)
|
|
100人以下(努力義務)
|
・①、②のすべての項目から任意の項目を1項目以上
|
・①、②のすべての項目から任意の項目を1項目以上(変更なし)
|
(3)法改正の時期
改正法の施行時期は、(1)は改正法の公布日、(2)については、2026年4月1日とされています。
3.改正法の影響
今回の改正により、2026年4月1日以降、101人以上の企業は自社の男女間の賃金差異や女性管理職比率等のデータを把握する必要が生じますので、早めの準備が肝要です。
次回は女性活躍推進法に基づき厚生労働省が認定する「えるぼし」認定に関する改正と制度概要を見ていきます。
▽女性活躍推進法の関連コラムをチェックする▽
2021.05.27 改正女性活躍推進法のポイント(101人以上の企業も行動計画の策定が義務化されます)
2022.02.01 2022年4月から適用事業主拡大!改正女性活躍推進法
2022.10.15 【法改正】女性活躍推進法~男女の賃金差異の開示義務化の概要について~
2022.11.01 【法改正!2022年7月以降の対応が必要です!】女性活躍推進法 男女の賃金差異の開示義務化の具体的な取扱い(前編)~厚生労働省のQ&A等をもとに賃金差異の算出方法を開設~
2022.11.15 【法改正!2022年7月以降の対応が必要です!】女性活躍推進法 男女の賃金差異の開示義務化の具体的な取扱い(後編))~厚生労働省のQ&A等をもとに賃金差異の算出方法を開設~