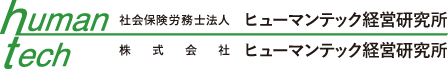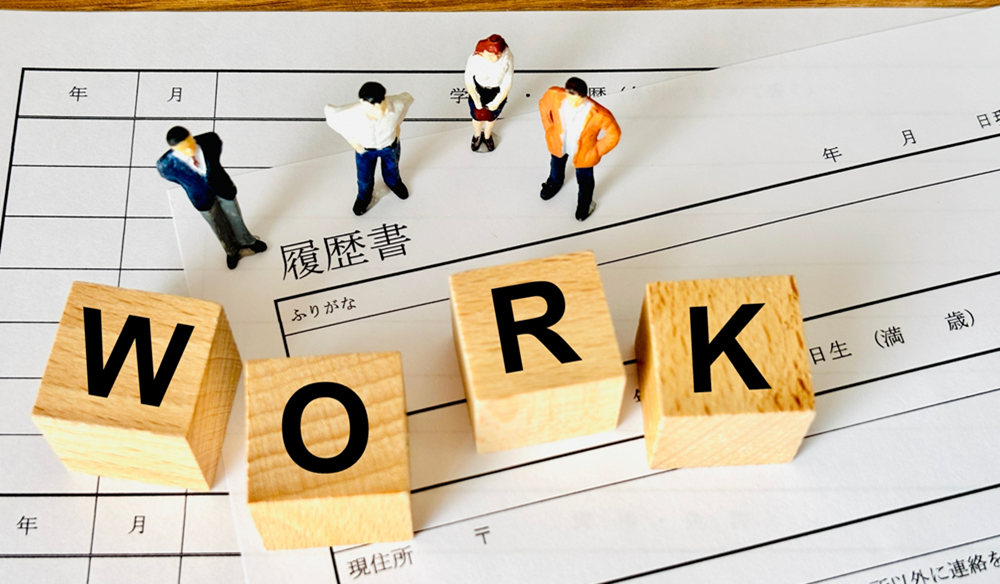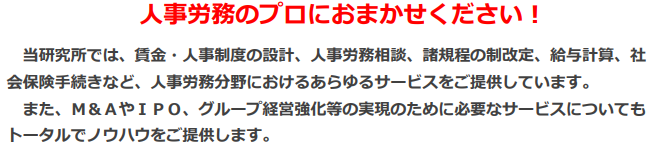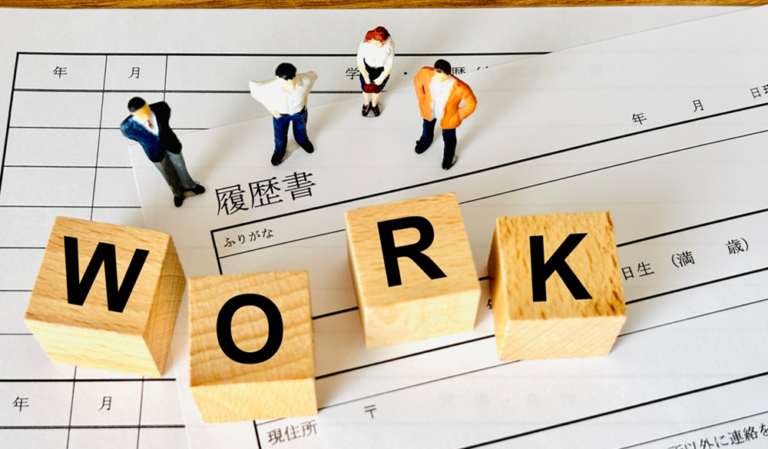2025.09.01
法改正情報
【2025年6月成立】就活ハラスメント防止措置の法制化と企業の対応実務
職場におけるハラスメントが社会問題となっている中、「労働施策総合推進法等の一部を改正する法律(※1)」が2025年の通常国会で成立し、6月11日に公布されました。本改正法には男女雇用機会均等法の改正が含まれています。この法改正に伴い、求職者等に対するセクシュアルハラスメント(いわゆる就活ハラスメント)を防止するための措置が事業主に対して義務づけられます。
そこで、今回は就活ハラスメントの内容と改正により事業主に義務づけられる措置について解説していきます。
※1 正式名称は「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律」という。
1.改正法の内容
(1)就活ハラスメントとは
「就活ハラスメント」とは、採用する企業やその採用担当者等が優越的な立場を利用して、就職活動中の学生等に行うセクシュアルハラスメント(以下「セクハラ」という。)やパワーハラスメント(以下「パワハラ」という。)をいいます。
現行の男女雇用機会均等法および労働施策総合推進法では、就活ハラスメントにかかる防止措置を講じることが企業に義務づけられておらず、あくまで「望ましい」取組みとされていますが、今回の改正により、就職活動中の学生等に対するセクハラを防止するための措置を講じることが企業に義務づけられます。なお、パワハラについては、今回は法改正の対象となりませんでした。
(2)就活ハラスメントの該当行為と実態
では、どのような行為が就活ハラスメントに該当するかについて見ていきましょう。2023(令和5)年度の厚生労働省「職場のハラスメントに関する実態調査」によると、就職活動中またはインターン中の学生に対するセクハラ(就活等セクハラ)を受けた場面として、最も割合が大きいとされるインターンシップ中にセクハラを経験した者は30.1%であり、その内容としては、「性的な冗談やからかい」(38.2%)と回答した割合が最も高く、次いで「食事やデートへの執拗な誘い」(35.1%)、「不必要な身体への接触」(27.2%)が続きます。本稿執筆時点では就活ハラスメントに該当する具体的な行為の内容について法令上明確に示されていませんが、厚生労働省のウェブサイト「あかるい職場応援団」に掲載されている研修資料では、具体的な行為として下記4つの例が挙げられています。
【図表1 就活ハラスメントに該当する行為の例】(※2)
| (ハラスメントの種類) | (該当行為の例) |
|---|---|
| 対価型セクハラ | 幹部社員が女子学生に対し、採用の見返りに不適切な関係を迫り、その後もメールやLINEで連絡を取り関係を迫った。これを女子学生が断ると、「うちの会社には絶対入社させない」と伝え、実際に不採用とした。 |
| 環境型セクハラ | 「つきあっている男性はいるか」「結婚や出産後も働き続けたいか」ということを女子学生にだけ質問した。 |
| パワハラ (過大な要求) |
内定した学生に対して研修と称し、内定者でつくるSNS交流サイトに毎日の書き込みを強要する。書き込みを行わない内定者に対して社員が「やる気がない、やる自信がないなら、辞退して下さい」 などの威圧的な投稿を度々行う。 |
| パワハラ (精神的な攻撃) |
面接の場で会社上層部や役員が学生に対し、高圧的な態度で人格を否定するような暴言を吐き、 学生を精神的に追い詰めた。 |
※2 厚生労働省ウェブサイト「あかるい職場応援団」ハラスメント対策研修動画「職場におけるハラスメント対策(就活ハラスメント対策)」資料より
(3)雇用管理上講ずべき措置
今回の改正法では、求職者等に対するセクハラを防止するための措置として、「求職者等からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置」を講じることが事業主に義務づけられます。具体的な措置の内容については今後指針において示される予定ですが、労働政策審議会の建議(※3)では以下のような内容を指針で示すことが適当とされています。
【図表2 建議で示された内容(一部)】
| ・ | 事業主の方針等の明確化に際して、いわゆるOB・OG訪問等の機会を含めその雇用する労働者が求職者と接触するあらゆる機会について、実情に応じて、面談等を行う際のルールをあらかじめ定めておくことや、求職者の相談に応じられる窓口を求職者に周知すること |
| ・ | セクシュアルハラスメントが発生した場合には、被害者である求職者への配慮として、事案の内容や状況に応じて、被害者の心情に十分に配慮しつつ、行為者の謝罪を行うことや、相談対応等を行うことが考えられること |
※3「女性活躍の更なる推進及び職場におけるハラスメント防止対策の強化について」
(4)不利益取扱いの禁止
事業主は、労働者が当該事業主による求職者等からの相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこととされています。
(5)勧告・公表
今回の改正法において罰則は設けられていませんが、(3)の雇用管理上講ずべき措置と(4)の不利益取扱いの禁止に違反していることに対して国から勧告を受けた事業主が勧告の内容に従わなかった場合、厚生労働大臣はその旨を公表できることとされています。
(6)施行時期
施行時期は、公布の日(2025年6月11日)から起算して1年6ヵ月以内の政令で定める日とされています。
2.おわりに
改正法施行後は、事業規模にかかわらず就活ハラスメントに対する措置を講ずる義務が生じます。まだ施行時期は明確になっていませんが、就業規則等の改定や相談窓口を整備する場合の相談員の教育・研修など、対応には一定の時間を要すると考えられるため、早めに対応することが望まれます。
以上
▽ハラスメントの関連コラムをチェックする▽
2020.4.1 職場におけるパワーハラスメントの法制化と防止対策
2024.5.15 フリーランス保護法~フリーランスの就業環境の整備と罰則の適用等の対応について~
2025.5.1 カスタマーハラスメントの法制化と企業の対応事項(前編)~これまでのカスハラ防止に関する措置の内容~(前編)
2025.5.15 カスタマーハラスメントの法制化と企業の対応事項(後編)~改正法の内容および企業の対応実務~