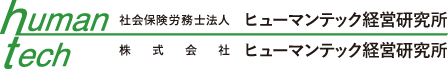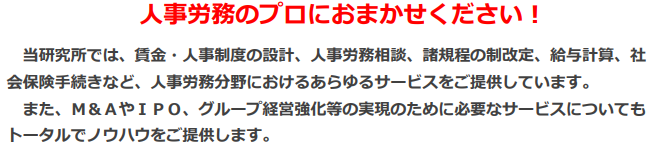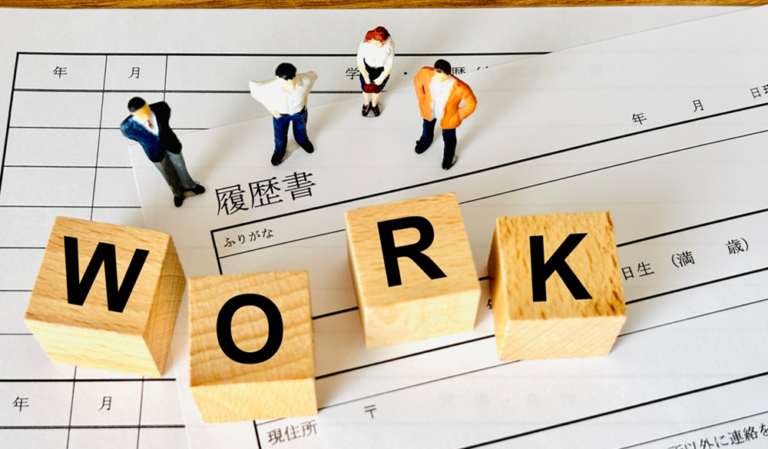2025.05.15
法改正情報
カスハラ防止措置の法制化と企業の対応事項(後編) ~改正法の内容および企業の対応実務~
近年、顧客等からひどい暴言や不当な要求など著しい迷惑行為を受ける、いわゆる「カスタマーハラスメント」(以下「カスハラ」という。)が社会問題になっています。前回はこれまでのカスハラ防止に関する政府や地方公共団体の動きについて解説しましたが、今回は、2025年6月11日に公布された「労働施策総合推進法(※1)等の一部を改正する法律案」のうち、カスハラ防止に関する改正法(以下「改正法」という。)の内容と企業の対応実務について確認していきます。
▽前回コラムをチェックする▽
カスタマーハラスメントの法制化と企業の対応事項(前編)~これまでのカスハラ防止に関する措置の内容~
目次
1.労働施策総合推進法の改正
企業のカスハラ防止対策に関しては、労働施策総合推進法に基づく現行の「パワハラ防止指針」において、取組みを行うことが「望ましい」とされているものの、カスハラ防止対策を講じることを企業に義務づける法律の定めはありません。
これに対して、今回の改正法では、カスハラが社会問題になっている背景を踏まえ、カスハラ防止対策の義務化が盛り込まれました。
2.改正法の内容
では、カスハラ防止対策が盛り込まれた労働施策総合推進法の改正内容について見ていきましょう。
(1)カスハラ行為の定義
改正法では、いわゆるカスハラ行為の定義について、以下のように定められています。
| ① 職場において行われる顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の当該事業主の行う事業に関係を有する者の言動であって、 |
| ② その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより |
| ③ 当該労働者の就業環境が害されること |
上記カスハラ行為の具体的な解釈については、今後、指針等で定めることとされています。この点について、労働政策審議会雇用環境・均等分科会の建議(「女性活躍の更なる推進及び職場におけるハラスメント防止対策の強化について」(以下「建議」という。))では、カスハラ行為について、①~③の要素をすべて満たすものであり、それぞれについて以下の事項を「指針等で示すことが適当」とされています。
①には、カスハラの行為者となり得る者が示されています。「顧客」には、今後利用する可能性がある潜在的な顧客も含まれます。「施設利用者」は施設を利用する者であり、施設の具体例としては、駅、空港、病院、学校、福祉施設、公共施設等が考えられるとされています。また、利害関係者(当該事業主の行う事業に関係を有する者)は、顧客、取引先、施設利用者等に限らず、さまざまな者が行為者として想定されていることを意図するものであり、法律上の利害関係だけでなく、施設の近隣住民等、事実上の利害関係がある者を含むとされています。
②の「社会通念上相当な範囲を超えた言動」とは権利の濫用・逸脱に当たるようなものをいい、社会通念に照らし、当該顧客等の言動の内容が契約内容からして相当性を欠くもの、または手段・態様が相当でないものが考えられるとし、そのような言動に当たるか否かの判断については、「言動の内容」および「手段・態様」に着目し、総合的に判断するものとされています。なお、「言動の内容」または「手段・態様」のいずれか一方のみであっても社会通念上相当な範囲を超えると、カスハラに該当すると判断されることがあり得ることに留意が必要とされています。
③の「労働者の就業環境が害されること」は、労働者が身体的または精神的に苦痛を与えられ、労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じることを意味し、その判断にあたっては、「平均的な労働者の感じ方」、すなわち「同様の状況で当該言動を受けた場合に、社会一般の労働者が、就業する上で看過できない程度の支障が生じたと感じるような言動であるかどうか」を基準とすることが適当とされています。
なお、建議では、顧客等からのクレームすべてがカスハラ行為に該当するわけではなく、客観的に見て、社会通念上相当な範囲で行われたものは、いわゆる「正当なクレーム」であり、カスハラ行為に該当するものではないことに留意する必要があることとされています。
(2)雇用管理上講ずべき措置
改正法では、事業主に対し、カスハラによって労働者の就業環境が害されることのないよう、労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上の措置を講じなければならないとされています。
会社が講ずべき措置の具体的な内容は指針等で示されることとなっており、現時点で詳細は不明ですが、建議では、具体的な措置の内容として、以下のような事項を指針で示すことが適当とされています。
| ・事業主の方針等の明確化およびその周知・啓発 |
| ・相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 |
| ・カスハラにかかる事後の迅速かつ適切な対応(カスハラの発生を契機としてカスハラの端緒となった商品やサービス、接客の問題点等が把握された場合には、その問題点等そのものの改善を図ることを含む。) |
| ・これらの措置とあわせて講ずべき措置 |
なお、これらの措置は、すでに労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法および育児・介護休業法で法制化されているパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントと基本的な内容は同じです。
(3)不利益取扱いの禁止
改正法では、労働者がカスハラの相談を行ったことまたは相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこととされています。
(4)事業主の責務
改正法には、カスハラに関する事業主、労働者および顧客等の責務がそれぞれ定められています。このうち、事業主の責務としては、カスハラへの労働者の関心と理解を深めるとともに、労働者が取引先等の労働者に対してカスハラを行わないよう研修その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる措置に協力する努力義務が定められています。また、事業主(法人の場合は役員)自身が取引先等の労働者に対してカスハラを行わないようにする努力義務が課されています。
(5)勧告・公表
今回の改正法に罰則は設けられませんが、(2)の雇用管理上講ずべき措置と(3)の不利益取扱いの禁止に違反していることに対して国から勧告を受けた事業主が勧告の内容に従わなかったときは、厚生労働大臣はその旨を公表できることとされています。
(6)施行時期
改正法の施行時期は、公布の日(2025年6月11日)から起算して1年6ヵ月以内の政令で定める日とされています。
3.企業の対応実務
2.(2)で述べたとおり、事業主には、カスハラ防止に関する事業主の方針の周知・啓発や、相談窓口の整備等の雇用管理上の措置を施行日までに必ず講じる義務が生じます。
また、前回見たとおり、現行の「パワハラ防止指針」においても、相談体制の整備や被害者への配慮のための取組みを行うことが望ましいとされており、被害防止のためにはマニュアル作成や研修を実施することが有効とされています。このマニュアル作成について、厚生労働省から「カスタマーハラスメント対策 企業マニュアル」が公表されているほか、モデル事業として業界別のマニュアル作成が進められており、現在は「スーパーマーケット業編」が公開されています。これらのマニュアルを参考にしながら、業種・業態等の必要性に応じて自社のマニュアルを作成することも考えられます。
4.おわりに
施行時期は公布の日(2025年6月11日)から1年6ヵ月以内ですが、3.で述べた事業主方針の内容の決定や周知のための就業規則等の改定、相談窓口を整備する場合の相談員の教育・研修、マニュアルの作成等には一定の時間を要します。今後の動向を確認しつつ、早めに自社のカスハラ防止対策の検討を始めることが肝要です。
以上
▽ハラスメントの関連コラムをチェックする▽
2020.4.1 職場におけるパワーハラスメントの法制化と防止対策
2024.5.15 フリーランス保護法~フリーランスの就業環境の整備と罰則の適用等の対応について~