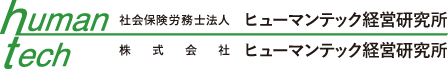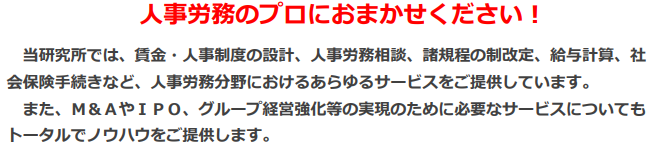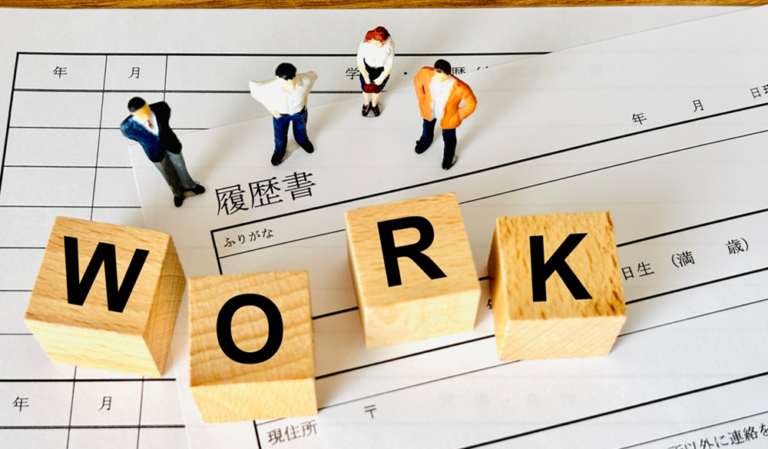2025.08.15
法改正情報
【2025年6月成立】年金制度が改正されます!! ~ iDeCoの加入可能年齢の上限引上げなど ~
2025年の通常国会で年金制度改正法※1が成立し、6月20日に公布されました。前回に引き続き、今回も改正法の概要について解説していきます。
※1 正式名称は「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」という。
▽前回コラムをチェックする▽
【2025年6月成立】年金制度が改正されます!! ~ 社会保険の適用拡大など ~
1.改正の全体像
年金制度改正法の改正事項は多岐にわたりますが、実務に影響のあるポイントをまとめると以下のとおりです。前回は以下の【図表1】のうち(1)~(3)をとり上げましたが、今回は(4)~(6)について解説します。
【図表1】年金制度改正法の改正の概要
| 改正事項 | 施行日 |
|---|---|
|
(1)社会保険の適用拡大等
|
改正事項により、
2026年10月1日
2027年10月1日
2029年10月1日
公布日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日
|
|
(2)在職老齢年金制度の見直し
|
2026年4月1日
|
|
(3)厚生年金保険等の標準報酬月額の
上限の段階的引上げ |
2027年9月1日
|
|
(4)遺族年金の見直し
|
2028年4月1日
|
|
(5)私的年金制度の見直し
|
改正事項により、
公布日から起算して3年もしくは5年を
超えない範囲内において政令で定める日
|
|
(6)その他年金制度にかかる見直し
|
改正事項により異なる
|
2.改正ポイントの解説
では、遺族年金の見直し、私的年金制度の見直し、その他年金制度にかかる見直しの順にそれぞれ見ていきましょう。
(1)遺族年金の見直し[施行日:2028年4月1日]
遺族年金は、国民年金・厚生年金保険における被保険者または被保険者であった者で、一定の要件を満たす者(以下、「被保険者等」という。)が死亡した際、生計を維持されていた遺族が受け取ることのできる年金です。
遺族年金には「遺族厚生年金」と「遺族基礎年金」がありますが、今回の改正により両年金が見直されることとなりました。以下、主な改正について順番に見ていきます。
① 遺族厚生年金の見直し
現遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者等が死亡した際、その遺族である配偶者・子※2※3、父母、孫※2、祖父母のうち、最も順位の高い者が受け取れる年金です。
現行法では、配偶者の受給要件および給付内容には男女差があり、子のない男性は被保険者等との死別時点で55歳以上である場合に限り無期給付が支給される※4一方で、子のない女性は被保険者等との死別時点で30歳以上であれば無期給付、30歳未満であれば5年間の有期給付が支給されます。
今回の改正では、この男女差が解消され、子のない配偶者については男女ともに、被保険者等との死別時点で60歳未満であれば原則5年間の有期給付、60歳以上であれば無期給付が支給されることとなります(【図表2】参照)。
ただし、改正前から遺族厚生年金を受給していた配偶者や、2028年度に40歳以上になる妻の給付内容については、この見直しの影響は受けません。
| 【図表2】子のない配偶者の受給要件と給付内容 |
 |
この改正に伴い、遺族となる配偶者の収入要件(年収850万円未満であること)の廃止、死亡した被保険者等の老齢厚生年金相当額の一部を遺族厚生年金に上乗せする「有期給付加算」の創設、婚姻期間中の厚生年金記録を分割して遺族の記録に上乗せして老齢厚生年金を増加させる「死亡分割」の創設、収入が十分でない等配慮が必要な場合の5年目以降の給付継続等の配慮措置が実施されます。
たとえば、子のない30歳の夫が妻を亡くした場合、【図表3】のような配慮措置が受けられる可能性があります。
| 【図表3】子のない30歳の夫が妻を亡くした場合の配慮措置の例 |
 |
| (資料出所:厚生労働省「改正事項について解説した補足資料(詳細版)」) |
②遺族基礎年金の見直し
遺族基礎年金は、国民年金の被保険者等が死亡した際、その遺族のうち、子のある配偶者または子が受け取れる年金です。現行の制度では、以下のa)b)いずれかの状態にある間は子の遺族基礎年金は支給停止となりますが、今回の改正でb)が廃止されることとなりました。
|
a)子のある配偶者が遺族基礎年金を受け取っている
b)子に生計を同じくする父または母がいる(廃止)
|
この改正により、父母の都合等に左右されることなく、子が遺族基礎年金を受給できるようになります。たとえば、以下の【図表4】のようなケースにおいて、改正前は遺族基礎年金を受給できなかった子が受給できるようになります。
| 【図表4】改正により、子が遺族基礎年金を受給できるようになる事例 |
 |
| (資料出所:厚生労働省「改正事項について解説した補足資料(概要版)」) |
(2)私的年金制度の見直し
ここまで公的年金制度の改正について見てきましたが、公的年金の上乗せを保障する私的年金制度についても以下のような見直しが行われています
① iDeCo(個人型確定拠出年金)の加入可能年齢の上限引上げ[施行日:公布日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日]
現行のiDeCoは、老齢基礎年金やiDeCoの老齢給付金を受給していない国民年金被保険者であることが加入要件とされており、働き方などによって加入年齢の上限が60歳または65歳とされています。今回の改正において加入要件が拡充され、国民年金被保険者のほか、私的年金を活用した老後の資産形成を継続しようとする者(具体的には、以下のa)b)のいずれかに該当する者)であれば、働き方に関係なく70歳までiDeCoの加入・継続拠出が認められることとなりました(【図表5】参照)。
| 老齢基礎年金やiDeCoの老齢給付金を受給していない者のうち、
a)iDeCoの加入者・運用指図者
b)企業型DC等の私的年金の資産をiDeCoに移換する者
|
| 【図表5】iDeCoの加入可能年齢の上限引上げ |
 |
| (資料出所:厚生労働省「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための 国民年金法等の一部を改正する等の法律の概要」) |
②企業型DC(企業型確定拠出年金)拠出限度額の拡充[施行日:公布日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日]
企業型DCの加入者が、事業主の拠出に上乗せして掛金を拠出するマッチング拠出において、加入者掛金が事業主掛金の額を超えられないという制限が撤廃されます。
③企業年金の運用の見える化[施行日:公布日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日]
現在、企業年金の運営状況については厚生労働省への報告書の提出義務があるものの、その情報は一般には公開されていません。企業年金の実施主体等が他社との比較・分析により運営を改善することに資するため、厚生労働省が情報を集約して公表する旨の規定が新設されました。
(3)その他年金制度にかかる見直し
年金制度改正法では、前述した改正事項のほかにも所要の改正が行われました。公的年金制度においては、子のある年金受給者に対する加算額の引上げ※5や、脱退一時金の支給要件の見直し※6等がなされ、私的年金制度においては簡易型DC制度の見直し※7等が盛り込まれています。
3.おわりに
前回から2回にわたり、2025年の通常国会で成立した年金制度改正法の概要を解説してきました。施行日が未定の改正もありますので、今後の動向にも注意しつつ、改正法への対応を進めていく必要があります。
以上
▽年金制度関連コラムをチェックする▽
2021.9.1 【2024年10月】短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の段階的拡大(前編)
2021.9.15 【2024年10月】短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の段階的拡大(後編)
2024.1.1 わかりやすく解説!年収の壁とは~106万円・130万円の壁について~(前編)
2024.1.15 わかりやすく解説!年収の壁とは ~年収の壁・支援強化パッケージについて~(後編)
2024.9.1 【106万円の壁問題に関連!】常時雇用51人以上の企業における社会保険の適用拡大