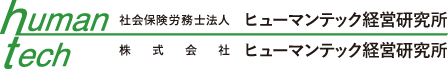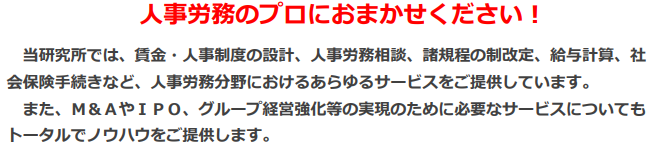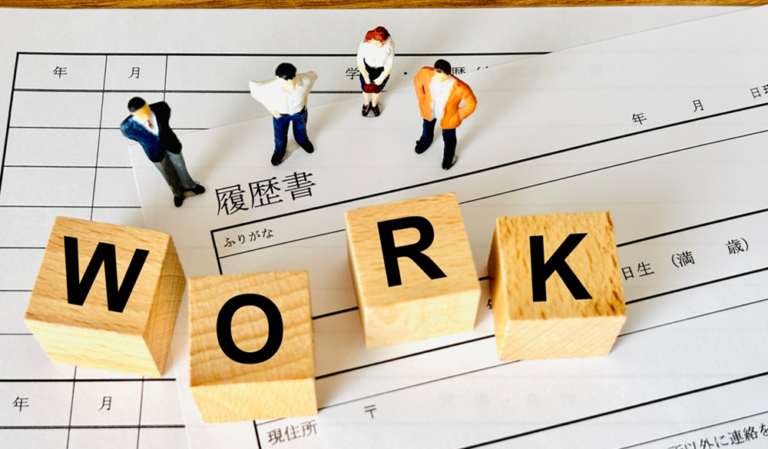2025.04.15
法改正情報
労働基準関係法制研究会報告書の概要(後編) ~ 今後の労基法改正の方向性(労働時間法制の具体的課題)について解説! ~
労働基準関係法制研究会(以下「研究会」という。)より2025年1月8日付で「労働基準関係法制研究会報告書」(以下「報告書」という。)が公表されました。前回は、報告書のうち「労働基準関係法制に共通する総論的課題」の章について解説しましたが、今回は「労働時間法制の具体的課題」の章のポイントを解説していきます。
▽前回コラムをチェックする▽
労働基準関係法制研究会報告書の概要(前編)
~ 今後の労基法改正の方向性(総論的課題)について解説! ~
1.「労働時間法制の具体的課題」の論点
「労働時間法制の具体的課題」として、次の3つの論点が挙げられています。
| 1. | 最長労働時間規制 |
| 2. | 労働からの解放に関する規制 |
| 3. | 割増賃金規制 |
以下、それぞれの内容について見ていきましょう。
2.最長労働時間規制
労働基準法においては、法定労働時間、時間外・休日労働時間の上限規制、変形労働時間制、フレックスタイム制等により労働時間の規制がなされています。そこでまず、労働時間の長さを規制するこれらの「最長労働時間規制」についてポイントとなる事項を見ていきます。
(1)時間外・休日労働時間の上限規制
時間外・休日労働時間の上限規制(原則:月45時間・年360時間/特別条項:単月100時間未満・複数月平均80時間以内・年720時間)は2019年4月より導入され、すでに5年が経過しています。
報告書では、上限規制による効果を一定程度認めつつも、2020年以降は新型コロナウイルス感染症の影響が無視できないとして、「現時点では上限そのものを変更するための社会的合意を得るためには引き続き上限規制の施行状況やその影響を注視することが適当」とされています。
(2)企業による労働時間の情報開示
報告書では、上記(1)で述べた労働基準法の強行的な規制による労働時間短縮のほか、労働市場の調整機能を通じて、個別企業の勤務環境を改善していくことが考えられるとされています。このため、労働者が就職・転職にあたって各企業の労働時間の長さなどの情報を十分に得て就職・転職先を選べるよう、とくに企業の時間外・休日労働の実態について、企業外部への正確な情報開示が望ましいとされています。また、これらの情報を一覧で閲覧できるようにするため、その情報開示の基盤を整えることや義務的な情報開示について、厚生労働省に対し不断の取組みを期待するとされています。
他方で、企業内部への情報開示についても、個別企業の勤務環境の改善、労働基準法違反の状態の発生防止や迅速な是正につながることから、企業内部の開示・共有について、誰に対して、どのような目的で開示・共有し、何を改善していくのかを整理することが必要とされています。
(3)テレワーク等の柔軟な働き方
テレワーク等の柔軟な働き方については、①フレックスタイム制の改善、②テレワーク時のみなし労働時間制という2つの論点が挙げられています。以下、ポイントを見ていきます。
①フレックスタイム制の改善
テレワークを行う場合には、1日の勤務の中で労働の時間と家事や育児等の労働以外の時間が混在することにより、中抜け時間が発生する可能性があります。この点について報告書では、テレワーク時の労働時間制度についてフレックスタイム制を活用することが考えられるものの、現行制度では、フレックスタイム制を部分的に適用することはできず、テレワーク日と通常勤務日が混在するような場合にフレックスタイム制を活用しづらい状況があると課題を指摘しています。
その上で、テレワーク日と通常勤務日が混在するような場合にも活用しやすいよう、特定の日については労働者が自ら始業・終業時刻を選択するのではなく、あらかじめ就業規則等で定められた始業・終業時刻どおり出退勤することを可能とすることにより、部分的にフレックスタイム制を活用できる制度の導入を進めることが考えられるとされています。なお、この改善については、テレワークの場合に限らず取り組むべきとされています。
②テレワーク時のみなし労働時間制
報告書では、仕事と家庭生活が混在し得るテレワークについて、「実労働時間」ではなく「みなし労働時間」とすることがより望ましいと考える労働者が選択できる制度として、実効的な健康確保措置を設けた上で、在宅勤務に限定した新たなみなし労働時間制を設けることが考えられるとされています。この場合、集団的合意に加えて個別の本人同意を要件とすること、制度の適用後も本人同意の撤回を認めることを要件とすること等が考えられるとされています。
一方で、このみなし労働時間制については、長時間労働防止の観点から研究会で様々な懸念や意見が示されたこと等を踏まえ、継続的に検討していくことが必要とされています。
(4)法定労働時間週 44 時間の特例措置
常時10人未満の労働者を使用する商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業においては、法定労働時間を週44時間とする特例措置が設けられています(労働基準法施行規則25条の2)が、報告書では、特例措置対象事業場の87.2%が特例措置を使用していないとの調査結果(※)から、概ね制度の役割を終えていると指摘しています。この点、より詳細な実態把握とともに、特例措置撤廃に向けた検討に取り組むべきとされています。
※厚生労働省が委託して実施したPwCコンサルティング合同会社「労働時間制度等に関するアンケート調査」(2024年)
(5)実労働時間規制が適用されない労働者に対する措置(管理監督者)
現行の労働基準法において、実労働時間規制から外れる裁量労働制や高度プロフェッショナル制度には健康・福祉確保措置が設けられていますが、同じく実労働時間規制から外れる管理監督者には同措置が設けられていません。このため、報告書では、管理監督者等に関する健康・福祉確保措置について、検討に取り組むべきとされています。
また、本来は管理監督者等に当たらない労働者が管理監督者等として扱われている場合があると考えられることから、制度趣旨を踏まえて、その要件を明確化することが必要とされています。
3.労働からの解放に関する規制
労働基準法では、2.の「最長労働時間規制」のほか、労働者が労働から解放される時間をどれくらい確保しなければならないかという「労働からの解放に関する規制」が定められています。そこで、この規制に関する報告書の内容を見ていきます。
(1)休憩
労働基準法では、使用者は労働時間が6時間を超える場合には少なくとも45分、8時間を超える場合には少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないとされています(同法34条1項)。
報告書では、1日8時間を大幅に超えて長時間労働する場合に追加の休憩を義務づけることや、休憩の一斉付与を見直すか否か等について議論されたものの、いずれも現時点で法律の改正が必要との結論には至らなかったとされています。
(2)休日
休日については、①定期的な休日の確保、②法定休日の特定という2つの論点が挙げられています。以下、ポイントを見ていきます。
①定期的な休日の確保
現行の法定休日は4週4休を認めており(労働基準法35条2項)、理論上休日労働の扱いをせずに最大48連勤が可能となっています。また、36協定で休日労働の回数について締結をする場合にも、回数に上限がないことから、協定の範囲内で無制限に連続勤務させることが可能です。
このような現行の制度について、報告書では、労災保険における精神障害の認定基準では、休日のない2週間以上の連続勤務が心理的負荷となる具体的出来事の一つと示されていることを踏まえ、「13日を超える連続勤務をさせてはならない」旨の規定を労働基準法に設けるべきとされています。
②法定休日の特定
現行の労働基準法には法定休日の特定について定めがありません。この点について報告書では、法定休日は労働者の健康を確保するための休息であるとともに、労働者の私生活を尊重し、そのリズムを保つためのものであり、また、法定休日に関する法律関係が当事者間でも明確に認識されるべきであることから、あらかじめ法定休日を特定すべきことを法律上に規定すべきとされています。
(3)勤務間インターバル
勤務間インターバル制度とは、終業時刻から次の始業時刻の間に一定の休息時間(インターバル)を確保するしくみですが、現行は労働時間等設定改善法において努力義務が課されているものの、インターバルの時間数や対象者その他導入にあたっての留意事項は法令上示されていません。また、現状では導入企業がかなり少ないことが指摘されています。
このため、報告書では、勤務間インターバル制度の抜本的な導入促進と義務化を視野に入れつつ、法規制の強化について検討する必要があるとされています。
(4)つながらない権利
労働契約上、労働時間ではない時間に使用者が労働者の生活に介入する権利は本来ありませんが、現実には、突発的な状況への対応や顧客からの要求等によって勤務時間外に対応を余儀なくされる状況が発生します。この点について、欧州では就業時間外にメール等での業務連絡を受けない「つながらない権利」が提唱されており、フランスでは法制化されています。
報告書では、これらを踏まえ、勤務時間外にどのような連絡まで許容でき、どのようなものは拒否できるか、業務方法や事業展開等を含めた総合的な社内ルールを労使で検討する際に役立つガイドラインの策定等を検討することが必要とされています。
(5)年次有給休暇制度
年次有給休暇(以下「年休」という)については、時季指定義務の日数や長期間の年休取得の推進などさまざまな論点が挙げられています。以下、ポイントを見ていきます。
①年5日の年休時季指定義務や時間単位年休の上限(5日)の変更について
年休が10日以上付与される労働者に対する「5日」の年休の時季指定義務(労働基準法39条7項)、について、現在の5日間からただちに日数を変更すべき必要性があるとは思われないとされています。
また、同様に、時間単位年休(労働基準法39条4項)の上限日数(5日)についても、現在の上限5日間からただちに上限を変更すべき必要性があるとは思われないとされています。
②長期間の年休連続取得の推進について
ILO132号条約において、計画的・長期間の年休は、年休の権利を確保するため少なくとも中断されない2週間からなるものとすべきとされています。
この点、本報告書では、欧州と比較して我が国の労働者に長期休暇・バカンスのニーズがどの程度あるのか等を含め、中長期的な検討が必要とされています。
③育休復帰者や退職労働者に関する残期間の年休時季指定義務の取扱いの改善
1年間の付与期間の途中に育児休業から復帰または退職する者など、付与期間の残りの労働日が著しく少なくなっている労働者に対してまで、他の労働者と同じ日数の時季指定義務を課すことは、使用者や労働者にとって不合理な制約になる場合があることからも、取扱いを検討することが必要とされています。
④年休取得時の賃金の算定方法における金額の妥当性
年休期間中の賃金については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、次のいずれかの方法で支払わなければならないとされています(労働基準法39条9項)。
| (a) | 労働基準法12条の平均賃金 |
| (b) | 所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金 |
| (c) | 当該事業場の労働者の過半数代表との労使協定により、健康保険法上の標準報酬月額の30分の1に相当する額 |
この定めについて、日給制・時給制の場合等において(a)や(c)の方法がとられた場合、計算上、賃金が大きく減額され得るため、(a)や(c)の手法をとらざるを得ない状況としてどのようなものがあるのかを考慮しつつ、原則として(b)の手法をとるようにしていくべきと考えらえるとされています。
4.割増賃金規制
労働基準法には、時間外・休日労働、深夜労働といった割増賃金規制が定められています。そこで、最後に、この割増賃金規制について、報告書の内容を見ていきます。
(1)割増賃金の趣旨・目的
報告書では、割増賃金の趣旨・目的として、①通常の勤務時間とは異なる時間外・休日・深夜労働をした場合の労働者への補償、②使用者に対して経済的負担を課すことによる労働の抑制の2点が挙げられています。
研究会では、上記の趣旨・目的を基礎に現在の働き方の多様化等を踏まえて割増賃金の機能、課題について議論が行われ、さまざまな意見が挙げられました。
報告書では、割増賃金にかかる実態把握を含めた情報収集を進め、中長期的に検討していく必要があるとされています。
(2)副業・兼業の場合の割増賃金
現行では、労働基準法38条に基づく通達により、労働者が複数の事業場で働く場合、事業主が異なる場合でも労働時間を通算して割増賃金を支払うこととされています。このため、現在は副業・兼業における割増賃金の支払いは、以下のいずれかの方法による必要があります。
| ① | 厚生労働省のガイドラインに基づき、労働契約の締結の先後の順に所定労働時間を通算し、次に所定外労働の発生順に所定外労働時間を通算することによって割増賃金を計算する方法 |
| ② | あらかじめ設定したそれぞれの事業場における労働時間の範囲内で労働させる管理モデルを利用する方法 |
この取扱いについては、複雑な制度運用が求められ、副業・兼業が広がらない要因となっている可能性があること、また、海外では割増賃金の支払いにおいて労働時間の通算を行うしくみとはなっていないことが指摘されています。
報告書では、こうした現状を踏まえ、労働者の健康確保のための労働時間の通算は維持しつつも、割増賃金の支払いについては通算を要しないよう、制度改正に取り組むことが考えられるとされています。
5.おわりに
今回は労働基準関係法制研究会報告書における「労働時間法制の具体的課題」について解説しました。今後は、本報告書を踏まえ、来年の労働基準法改正を見据えながら、労働政策審議会において議論が進められる予定となっており、引き続き注視していく必要があります。
以上
▽労働基準法の関連コラムをチェックする▽
【2024年4月改正】労働条件明示ルールの変更(前編)~ 無期転換に関する明示ルールの見直し ~
【2024年4月改正】労働条件明示ルールの変更(後編)~ 労働条件の明示事項に新たな項目が追加されます ~
【2024年4月改正】裁量労働制の見直しについてわかりやすく解説(前編)~ 専門業務型裁量労働制の改正内容 ~
【2024年4月改正】裁量労働制の見直しについてわかりやすく解説(後編)~ 企画業務型裁量労働制の改正内容 ~